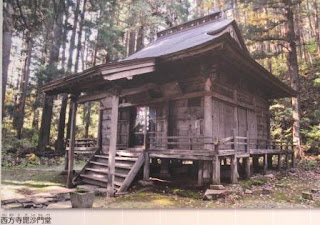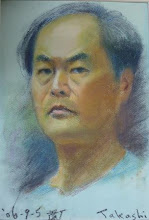↓山門を潜った参道の紅葉も好調
しかし参道の奥に行くとモミジの葉は緑々している。左に折れた赤門前の参道もこの調子
↓お目当ての「明壽院庭園」に入る
↓桃山時代の庭園
白いお堂は不動堂
↓不動堂に隣接した茶室
↓江戸時代中期の庭園
血染めのモミジ
ドウダンツツジ
茶室の前
↓本堂に登る参道入口
本堂二天門直下まで子地蔵の列が続く。左右一対ずつ500対、合計1000体。
途中脇の広場に子地蔵達が団体で整列している箇所が3箇所はあるので、子地蔵の聡合計は1500体は下るまい。
二天門がようよう見えてきた。普通足の方が降参している。
二天門に最寄りの子地蔵さんの番号「壱」番(お向さんが弐番)
↓二天門を潜ると、国宝本堂
本堂側面。こちらから本堂に出入する。
↓左の高台に重文三重塔↓長い下り坂を下り切って登り口の子地蔵さんの番号を確認すると、1000番。お向さんは999番。
〇金剛輪寺の紅葉の具合は、最盛紅葉の8割と判定。しかし緑が赤に変わるとき、赤は落葉となるので判定は難しい。