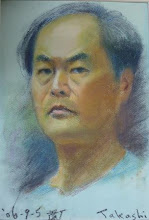〇朝来から鳥取まで100km近くあった。10時半、鳥取城に到着。城の扇御殿後に明治40年に建築された重文「仁風閣」を見学。この洋館は、大正天皇が皇太子時代に鳥取県に行啓されたとき、その行在所として元鳥取藩主池田侯爵が馳走した。
↓久松山。山頂に天守があった。
↓城の石垣と仁風閣
↓二階の食堂
〇倉吉に寄ることに。三朝(みささ)温泉を通るルートを行く。国宝「投入堂」で有名な三徳山(みとくさん)三仏寺の前を通る。この寺、ボクは何年か前に訪ねた。どうしても国宝や重文の建造物に逢いたくて。しかし何と、連れがないと(単独行では)それらの建物がある危険な山中には立入禁止。そこはロッククライミングの場面が続く修験道の世界らしい。こんな寺は外にない。
倉吉は、白壁の蔵と赤瓦の街並で聞こえる。一見するために寄った。
↓たい焼き・たこ焼き店。たい焼き一匹を買い食い。
〇蒜山高原に登る。岡山県にある。子供達と行った時の美しい風景が忘れられずにもう一度行ってみることに。しかし低気圧が来ているらしく小雨模様で大山は見えず仕舞い。凍えた。ボクが絵を描いている間に子供達が遊んだレジャーランドは今もあった。
↓晴れれば大山が見える
〇かつて夕陽を背景に見た船上山(せんじょうせん)にも再訪。衝撃的な姿の山だった(マグマが冷えて柱状節理を成している。東尋坊が山の上にあると思えば分りが好い)。それが逆光で好い写真が残らなかったので再挑戦することに。ところが小雨の中の撮影となり今回もまた好い写真にならなかった。
↑この山は日本史に登場する。後醍醐天皇が、島流しにされていた隠岐を脱出し名和氏が勢力を張っていた本土海岸に上陸し、地侍豪族の名和長年の加勢を得てこの船上山山頂の金石寺(こんしゃくじ)に立て籠もった。そして攻め上って来た北条方の軍勢を下して亰へ向かう。
〇船上山から日本海に向けて真っ直ぐ下って海岸に出たら道の駅赤崎があった。夕方6時。今日はここで泊まる。この道に泊るのは二度目ではないか。