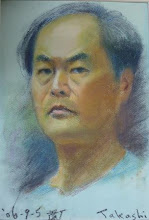〇《奥の細道》より。「廿余丁、山を登って滝有。岩洞の頂より飛流して百尺千岩の碧潭(へきたん・青い淵)に落たり。岩窟に身をひそめ入りて、滝の裏よりみれば、うらみの滝と申伝え侍る也。」
『暫時(しばらく)は滝に籠るや夏(げ)の初(はじめ)』
↑「裏見の滝 この滝は日光三名瀑の一つで、高さ約19m、幅約2mほどの比較的小さな滝です。滝を裏側から見ることができたため、この名がつけられました。芭蕉翁も奥の細道の旅の途中この地を訪ねております。寛永元年(1624年)奥州の出羽三山から荒沢不動尊が迎えられ、名僧天海の命によってこの滝のところに安置されました。そして男体山、太郎山、大真名子山への信仰登山のための修行場となり、以来この地は荒沢と呼ばれ、行屋や茶屋などもでき、大変栄えたところです。」 地図の左下から上中央にかけて斜めに三山が連なっているが、左下から男体山・大真名子山・女峰山、そして左上に太郎山。↓車で来れる終点。
↓ここでセレナを下りて歩き出すことになる。「裏見ノ滝 0.5km 」の地点。トレッキングシューズに履き替えていざ出発と思ったら、猛烈な豪雨となった。山道はたちまち川になった。しばらく様子を見たが雨脚は衰えそうにない。ので、芭蕉歌枕の眼目の一つ「裏見の滝」の探訪は断念。
↓これが「裏見の滝」だそう。水量によって全く違った風に見えるらしい。昔は滝の落ち口の岩頭が出っ張っていて滝の裏側に空洞があり、その空洞に入り込んで滝を裏側から見ることができたそう。今はその岩頭が崩れ落ちてかなわぬことらしい。
〇隆君の旅日記から
8/10(日)
06:45起床。07:50春日部・道の駅庄和、出発。出発に当たり、昨日旧日光街道上から撮影だけした東陽寺の境内に乗り入れた。芭蕉と曽良の二人旅の絵入りの大きな石碑、発見。
今日は先ず歌枕「室の八嶋」を目指す。芭蕉が奥の細道で訪ねた歌枕第一号。栃木市惣社町にある。下道を行く。古河(こが)宿、間々田(ままだ)宿、幸手(さって)宿、小山(おやま)宿と通過し、小山市喜沢で左折し壬生街道に入った。壬生は次女が六年間学生生活を送った所で懐かしい。室の八嶋までそう遠くなかった。
室の八嶋は「大神(おおみわ)神社」が正称。下野国総社。旧社格は県社。奈良県の大神神社の祭神・大物主命を分祀。いかにも県社という感じ。
この後、芭蕉と曽良は「金売吉次の墓」に立ち寄ったそう。しかし雨中、発見が無理そうなので飛ばした。後で楡木の追分辻で判明したが、ボクは金売吉次の墓に絶対巡り合わない道筋を走っていた。
曾良の随行記によると、芭蕉は室の八嶋を訪ねた日、鹿沼宿に泊まっている。宿泊先は書いてないが、太光寺という寺らしい。探し当てた。境内に芭蕉の笠塚があった。文面によると当時無住だったそう。今は膨大な数の墓を管理し、ひかり幼稚園を経営していて裕福そう。この寺で今日何度目かの豪雨に見舞われた。
鹿沼宿から今市宿を目指した。芭蕉は日光山を探訪するため日光例幣使街道を辿り今市宿で泊まった。鹿沼から今市まで続く例幣使街道(京から下向する例幣使が通る道)は一直線に北上する杉並木街道。杉並木がほぼ全線、それは見事に残っている。宇都宮から今市までの日光表街道の杉並木は有名だが、こちらの比ではない。
今市宿は今も栄えている。今市に入ったのは14:00過ぎ。雨も降っている。東照宮などの社寺群の見学は今日は無理と考えて、いろは坂を登り「黒髪山(男体山)」「華厳の滝」に会う日程を先に済ませておこうと考えて山に向かったら、「裏見の滝」の案内板が目に入った。いろは坂を登るずっと手前。芭蕉が探訪したことをわざわざ奥の細道に書き遺した滝。勿論ボクは反射的にハンドルを切って指し示された山奥に入り込んだが、駐車して歩く段になって猛然たる雨脚が山道を川にした。滝まで0.5km。探訪を断念したのが14:30、今日の日光拝観をすべて中止。断続的に豪雨が襲来。心なしか風も出てきた。台風11号が奈辺にいるのか、ボクには分らないがその影響が北関東にも及んできている。旅程が悪天候で二日潰れたら、今回の旅行は企画倒れだな。松島までも行けない。それに約束事に羈束された旅って、疲れるもんやなぁ。面白味にも欠けるし。