《奥の細道》《最上川のらんと大石田と云ふ所に日和を待つ。
爰(ここ)に古き俳諧の種(落ち)こぼれて、忘れぬ花のむかしをしたひ、蘆角(ろかく)(★註1)一声の心をやはらげ、此の道にさぐりあしして、新古ふた道にふみまよふといへども、みちしるべする人しなければと、わりなき一巻(を)残し(★註2)。このたびの風流、爰に至れり。
最上川は、みちのくより出て、山形を水上とす。ごてん・は やぶさなど云おそろしき難所有。板敷山の北を流て、果は酒田の海に入。左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。是に稲つみたるをや、いな船といふならし。白糸の 滝は青葉の隙々(ひまひま)に落て、仙人堂、岸に臨て立。水みなぎつて舟あやうし 。
五月雨をあつめて早し最上川》
最上川は、みちのくより出て、山形を水上とす。ごてん・は やぶさなど云おそろしき難所有。板敷山の北を流て、果は酒田の海に入。左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。是に稲つみたるをや、いな船といふならし。白糸の 滝は青葉の隙々(ひまひま)に落て、仙人堂、岸に臨て立。水みなぎつて舟あやうし 。
★註1 「蘆角」 アシの笛という意味ではないかという説有り。辺鄙な田舎という程度の意味という説も有り
★註2 「わりなき一巻を残しぬ」 断るわけにもいかなくて歌仙一巻を残した。《さみだれをあつめてすゞし最上川》を発句とする一巻。当初の句は「早し」ではなくて「涼し」だった。
〇《奥の細道》を読むと、大石田で最上川を下る舟に乗ったかのように見える。しかしそうではなくて、大石田には「一栄」宅に5月28日から30日まで逗留し、それから馬で北の船形を通って(船形では猿羽根(さばね)峠を越えている)新庄に向かい、新庄の風流宅で6月1日2日と俳諧三昧の日を過ごしている。新庄を立ち、最上川の下り舟に乗ったのは3日である。乗船地は元合海(もとあいかい・今の地名は本合海)だった。新庄・本合海間は長い山道を西に辿る。
〇ところが、《奥の細道》には「新庄行き」のくだりが全く出てこない。割愛されている。何故なのか?新庄市民はさぞかし不本意だろう。尾花沢は《奥の細道》に載った御蔭で今もそして未来永劫に名誉を受け、観光資源の利益も享受するだろう。それに引き比べて新庄市民の無念はいかばかりかはかりしれない、と思われるが、実際新庄に行ってみると恨み言のかけらもない。芭蕉がわざわざ足を運んでくれたことへの感謝の念がある。《奥の細道》で無視されたことを決して恨んでいないのだ。
ボクの今回の奥の細道紀行での最大の疑問は、新庄が何故《奥の細道》で無視されたのかということ。《曾良随行日記》を読むと、芭蕉が《奥の細道》紀行で訪れた所のうち、ある所を軽視・無視するのにはある癖(へき)があることが分る。その癖というのは、不人情・理不尽な目に遭わされた場合に発現する。石巻の段、越後路の段に現れている。しかし、新庄で芭蕉は決して冷遇されていない。むしろ厚遇されている。活発に俳諧普及活動も行っている。このことは《曾良随行日記》を読めば分る。
『〇六月朔(一日) 大石田を立つ。辰刻(たつのこく・午前8時)、一栄・川水、弥陀堂迄送ル。馬二疋、舟形迄送ル。‥‥舟形‥‥二リ(里)八丁新庄。風流ニ宿ス。
二日 昼過ぎより九郎兵衛へ被ㇾ招(まねかれる)。彼是(かれこれ)、歌仙一巻有り。盛信(宅)。息(やすむ)、塘夕、渋谷仁兵衛、柳風共。孤松、加藤四良兵衛。如流、今藤彦兵衛。木端、小村善衛門。風流、渋谷甚兵ヘ(衛)(風流は、尾花沢へも早速に駆けつけてきた)。
〇三日 天気吉。新庄ヲ立ち、一リ(里)半、元合海。‥‥』
芭蕉を慕って人も集まり、歌仙も巻いているのだ。新庄が《奥の細道》で無視されたのは、芭蕉の不興・不快感とは全く無関係の事情によるものと見なければなるまい。
この疑問に答えるには、現地を踏破してみるしかない。現地を知る者には《奥の細道》という文学作品の中で展開される最上川後段の次のクライマックスシーンの文章が読者に意図的に感銘を与えるためにわざと誤解を生ずるように構成されていることが分る。
《奥の細道》《最上川はみちのく(米沢)より出(いで)て、山形を水上(みなかみ)とす。ごてん・はやぶさなど云ふ、おそろしき難所有り。板敷山(いたじきやま)の北を流れて、果ては酒田の海に入る。左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。是に稲つみたるをや、いな(稲)船といふならし。白糸の滝は、青葉の隙々(ひまひま)に落ちて、仙人堂岸に臨んで立つ。水みなぎつて、舟あやうし。五月雨をあつめて早し最上川 』
〇《奥の細道》を読むと、大石田で最上川を下る舟に乗ったかのように見える。しかしそうではなくて、大石田には「一栄」宅に5月28日から30日まで逗留し、それから馬で北の船形を通って(船形では猿羽根(さばね)峠を越えている)新庄に向かい、新庄の風流宅で6月1日2日と俳諧三昧の日を過ごしている。新庄を立ち、最上川の下り舟に乗ったのは3日である。乗船地は元合海(もとあいかい・今の地名は本合海)だった。新庄・本合海間は長い山道を西に辿る。
〇ところが、《奥の細道》には「新庄行き」のくだりが全く出てこない。割愛されている。何故なのか?新庄市民はさぞかし不本意だろう。尾花沢は《奥の細道》に載った御蔭で今もそして未来永劫に名誉を受け、観光資源の利益も享受するだろう。それに引き比べて新庄市民の無念はいかばかりかはかりしれない、と思われるが、実際新庄に行ってみると恨み言のかけらもない。芭蕉がわざわざ足を運んでくれたことへの感謝の念がある。《奥の細道》で無視されたことを決して恨んでいないのだ。
ボクの今回の奥の細道紀行での最大の疑問は、新庄が何故《奥の細道》で無視されたのかということ。《曾良随行日記》を読むと、芭蕉が《奥の細道》紀行で訪れた所のうち、ある所を軽視・無視するのにはある癖(へき)があることが分る。その癖というのは、不人情・理不尽な目に遭わされた場合に発現する。石巻の段、越後路の段に現れている。しかし、新庄で芭蕉は決して冷遇されていない。むしろ厚遇されている。活発に俳諧普及活動も行っている。このことは《曾良随行日記》を読めば分る。
『〇六月朔(一日) 大石田を立つ。辰刻(たつのこく・午前8時)、一栄・川水、弥陀堂迄送ル。馬二疋、舟形迄送ル。‥‥舟形‥‥二リ(里)八丁新庄。風流ニ宿ス。
二日 昼過ぎより九郎兵衛へ被ㇾ招(まねかれる)。彼是(かれこれ)、歌仙一巻有り。盛信(宅)。息(やすむ)、塘夕、渋谷仁兵衛、柳風共。孤松、加藤四良兵衛。如流、今藤彦兵衛。木端、小村善衛門。風流、渋谷甚兵ヘ(衛)(風流は、尾花沢へも早速に駆けつけてきた)。
〇三日 天気吉。新庄ヲ立ち、一リ(里)半、元合海。‥‥』
芭蕉を慕って人も集まり、歌仙も巻いているのだ。新庄が《奥の細道》で無視されたのは、芭蕉の不興・不快感とは全く無関係の事情によるものと見なければなるまい。
この疑問に答えるには、現地を踏破してみるしかない。現地を知る者には《奥の細道》という文学作品の中で展開される最上川後段の次のクライマックスシーンの文章が読者に意図的に感銘を与えるためにわざと誤解を生ずるように構成されていることが分る。
《奥の細道》《最上川はみちのく(米沢)より出(いで)て、山形を水上(みなかみ)とす。ごてん・はやぶさなど云ふ、おそろしき難所有り。板敷山(いたじきやま)の北を流れて、果ては酒田の海に入る。左右山覆ひ、茂みの中に船を下す。是に稲つみたるをや、いな(稲)船といふならし。白糸の滝は、青葉の隙々(ひまひま)に落ちて、仙人堂岸に臨んで立つ。水みなぎつて、舟あやうし。五月雨をあつめて早し最上川 』
この後段を、最上川をめぐる地理の知識なしに読めば、芭蕉は、ごてん・はやぶさ・三ヶ瀬の最上川三大難所を乗り切って、仙人堂・白糸の滝を見物しながら最上川を下って行き、かの有名な「五月雨を集めて早し最上川」の句を詠んだように思うだろう。ところが、最上川のハイライトの三大難所は大石田の少し上流にあってそこは陸路を辿っている。乗船した本合海から下流には仙人堂と白糸の滝があるのみ。芭蕉の文学的創作癖はここにおいて躍如とする。「最上川の(乗)らんと大石田と云ふ所に日和を待つ」ときた後に「ごてん・はやぶさなど云ふ、おそろしき難所有り」とくれば、三大難所も通過したと思い込むだろう。芭蕉の筆は絶妙で、三大難所を乗り切ったとは書いてないが、読者は文脈に誘導されて舟で通ったかのように錯覚する。そうなれば、最上川紀行としては完璧になる。五月雨の句も輝く。五月雨を集めて早い水流の中、三大難所を乗り切ったとは、まさに「舟あやうし」だったことだろう。
ここに新庄往来のくだりが挿入されると、大石田・舟方・新庄・本合海間が(新庄を頂点とする三角形をなす)陸路だったことがあからさまとなり、最上川舟下りの詩想が壊される。芭蕉的センスにかかれば新庄は黙殺されるしかない悲運の街となる。さらに言えば新庄の不運を決定したのは、尾花沢との地理的位置関係にあった。両者は共に山形県(羽前国)の東北隅にあって隣り合っている(新庄が尾花沢の西北にある)。芭蕉の行程は、尾花沢からググッと南下して天童市の立石寺に至り、また北上して大石田経由で尾花沢地域を再通過してその西北の新庄に至っており、その旅程の線形は冗長で美しくないし、紀行文として緊張感がない。それに比べ天童から最上川三大難所を通過したかのように描いて河港大石田に俳友を訪ねて三泊し、そこから舟日和を待って最上川を名所を嘆賞しながら下って行くコースの線形とイメージは文学的に格段に旅情が溢れて美しい。この芭蕉の強烈な美意識がなせる技こそ新庄が《奥の細道》から抹殺された要因だろう。
〇芭蕉は大石田で迷っていたと思われる。
①ここから舟に乗り川下りを楽しみながら羽黒三山の麓に出ること。
②山形を訪れること。
③新庄に行き風流らと会って蕉風俳諧の種を蒔くこと。
迷いながら選択した旅程の線形は確かに美しくない。しかし有意義だった。新庄には今も芭蕉の足跡が鮮明に残り大切にされている。
①ここから舟に乗り川下りを楽しみながら羽黒三山の麓に出ること。
②山形を訪れること。
③新庄に行き風流らと会って蕉風俳諧の種を蒔くこと。
迷いながら選択した旅程の線形は確かに美しくない。しかし有意義だった。新庄には今も芭蕉の足跡が鮮明に残り大切にされている。

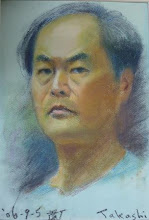
0 件のコメント:
コメントを投稿